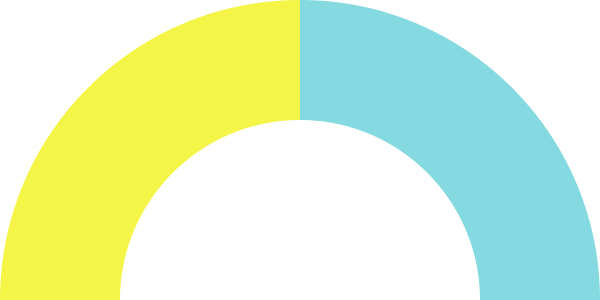日本ハムシステムソリューションズでは、多くの社員が仕事と育児を両立しながら活躍しています。
今回は、子育て世代の4名に集まっていただき、
日々の工夫や会社の制度活用、仲間からのサポートについて語ってもらいました。
member
-
O.Y
2022年 入社
統合システムサービス部標準化推進グループ
1歳半と生後0か月の子育て中。2人目の誕生を機に、在宅勤務を週2~3回と、16時半までの時短勤務に。
-
G.A
2020年 入社
セキュリティAIグループ
保育園に通う1歳4か月の子どもを持つ母。在宅での勤務とショートタイムフレックス制度を併用。
-
S.T
2021年 入社
セキュリティAIグループ
9か月の一人息子の保育園入園に向けて申請中。在宅勤務は週1~2日くらい。
-
T.Y
2022年 入社
管理・連結会計グループ
2025年4月に育休から復職。子どもは1歳8か月。勤務形態は時短勤務で、出社と在宅勤務は半々くらい。

01仕事と子育ての両立について
q両立するために職場や家庭で工夫していることはありますか?
-

T.Y
子どもの体調などで、急に早退したり、休まないといけなくなったりすることがあるので、それを前提にして行動しています。具体的には仕事のマニュアルをつくっておいて、私が急に休んだりしても、周りの方にスムーズにやっていただけるようにしています。それから、毎日の業務予定をカレンダーに登録して、みんなに共有しています。
家では、炊き込みご飯とか炊飯器で作れるメニューを充実させているところです。火を使わないで調理できるから、その時間子どもと遊んであげられるんです。 -

O.Y
これまでは妻が育休をとっていましたから、僕の仕事が遅れているときは残業して進めていました。でもこれからは僕が育休や時短勤務に入ることになっていて、今、仕事を部内で引き継いでいます。今後は「残業でなんとかなる」っていう考えをやめないと。4時半になったら、何があっても子どもが待っているので帰ります!
-

G.A
私も保育園に今年4月から子どもを預け始めて、風邪をひいたり、お腹を壊したり。いつ休まないといけないか本当に分からない状態。ですから、何かあっても仕事に穴を開けないように、何事も早めに進めることですね。スケジュールに余裕があったとしても、早めにしておかないと、精神的にも余裕を持てなくて。
それでも急に休んでしまったときにはチームのみんなに申し訳ないという気持ちになりますが、大丈夫だよってフォローしてくださる。その分できる業務では、どんどんお返ししていかなきゃって気持ちになりますね。
家では夫も家のことをやってくれます。私が子どもを寝かしつけたら、洗い物など、基本的に全部やってくれます。保育園の用意も「俺も全部できる」って自信持っていますよ。 -

O.Y
何かあった時のために、妻も夫も両方ができるのは大事ですよね。どちらかが子どもを見ればいい。そうできると、それぞれがプライベートの時間も楽しむこともできますよね。
-

S.T
うちの子どもは今9か月でまだ離乳食。ですから妻はほぼつきっきりです。たまに昼間僕がちょっと見ている間に、外出することはあるんですけど、一日空けるとかまだできないですね。
皆さんと違うのは、まだ妻が育休中で、家のことをやってくれているので、割と僕は仕事に集中できています。でも、できるだけ定時で上がって、帰ったらすぐ息子をお風呂に入れて、晩御飯を食べさせて。寝かしつけまではやっています。
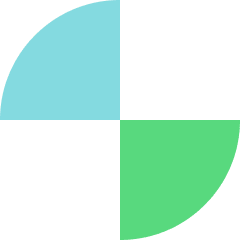


02育児に関する会社の制度や周囲の
バックアップについて
q皆さん、育休、時短勤務、リモートなどを利用しているんですね。
-

O.Y
育休は子どもが1歳まで2週間から1年の期間で、どのくらい取得するかは選べるんです。
-

G.A
1歳以降は、保育園に入れなかったら3歳まで延長できる。もし入れなくても安心だなぁって感じました。
-

S.T
そういえば、「時短」と「ショートタイムフレックス」ってありますよね。何が違うんですか?
-

G.A
ショートタイムフレックスは2025年の4月から導入された制度で、時短勤務の場合は月何時間とか、最初に1か月分を決めないといけない。でも、ショートタイムフレックスは自分で、日ごとに働く時間を決めることができます。この日は何時まで、この日は何時までという具合に、その日の業務量や、保育園のお迎えに合わせて、働く時間を変えられるんですよ。
q勤務時間に関すること以外で、子育てを応援する仕組みはありますか?
-

O.Y
制度的に一番ありがたいのは、次世代育成支援金(※1)ですよね。今は出産時に、国から50万円いただけるんですけど(※2)、クリニックによってはどうしても50万円をオーバーしてしまうことも。今回、妻が無痛分娩で出産したんですけど、やっぱり20万、30万って予算をオーバーしてしまったんです。急な出費をフォローできてありがたかった。
※1 次世代育成支援金…出産時に50万円のほか、その後入園時30万円、小学校入学30万円、中学入学30万円、高校入学50万円、大学入学50万円というように節目にも会社からお祝い金が支給される(支給要件あり)。
※2 出産育児一時金…公的医療保険の加入者が出産したとき、1人につき原則50万円が加入している保険者から支給される。 -

G.A
入社して最初にこの制度を知ったとき、「めっちゃいい!」ってなりました。
-

S.T
就職するときの決め手にもなりました。
-

T.Y
それに、特別有給もつきますよね。
-

O.Y
育休に入っても年間20日間の有給を付与してもらえる。給料を受け取りながら、休むことができる。めちゃくちゃありがたいです。
-

S.T
有給休暇とは別に、子どもの急な通院に使える看護休暇も助かっています。
-

G.A
看護休暇は時間単位で使えるのもいいですよね。午前だけ、午後だけでも使える。わたし、もう4日使いました。
-

T.Y
わたしも同じくらい利用してます!
03育児前と後での変化について
q子育てをするようになって仕事に対する考えや意識は変わりましたか?
-

T.Y
意識は変わりましたね。半年分のスケジュールを立てて、これやりましょうって決めています。ですが、やはり休むことが多くて、達成できてないこともたくさん。それで、反対に優先付けを大事にしようと。この仕事は何としてもこの日までに終わらせないといけないけど、別の仕事はもう1か月待ってもらえないかとか。上司と一緒に決めています。それでも期限に間に合わなさそうな時には早めに相談するようにしています。
-

O.Y
今は時短勤務中で、残業はできないのですが、僕の業務は打ち合わせが多くて、じっくり作業する時間がなかなか取れない。以前だったら残業で進めていたところなのですが……。ですから今は、打ち合わせの時間と自分の作業の時間をしっかり予定しておくことを意識しています。
-

S.T
私は効率をより考えるようになりました。後藤さんも言っていましたが、早め早めに全部していって、1人で悩みを抱え込まない。すぐ相談して、修正があったらすぐやって、みたいな感じです。
04子育ても仕事も、自分らしい方法を見つける
q最後に、子育てをしながら働けるかなと思っている人へのメッセージや、今後取り組みたいことがあれば教えてください。
-

T.Y
思った以上に子育てと仕事の両立は大変でした。保育園から急な呼び出しがあったり、思うように仕事が終わらなかったり。復職したての頃は、ミスを繰り返してしまうこともありました。育児休暇中と仕事のギャップに慣れるのに、時間がかかってしまい、自分を責めてしまったり……。それで思ったことは、ミスは次に生かして同じことは絶対間違えないようにするけど、完璧を目指さないでおこうと。子どもが生まれる前の、仕事に専念していた頃よりも少しハードルを下げて頑張っていきたい。
これから子育てされる方は、不安になったり、迷ったりすることもあると思うんですけど、その時に一人で抱え込まずに周りに頼りながら、自分らしいやり方を見つけていってほしい。 -

G.A
周りの人に助けられて、フォローしていただいている身なので、その分、子どもが大きくなって安定してきたら、逆に子育てしやすい職場環境を提供できるようにしていきたい。子育てをしやすい環境づくり、職場づくりっていうのは、次は私の番だと思ってやっていきたいなと今は思っています。今、恩恵を受けるばっかりだから。
-

O.Y
そうですね。仕事は組織で、子育ては家族でできるといいと思います。何においても個人でできることって限りがあるし、個人でやろうとすると、どうしても限界が来てしまう。どちらも、自分が抜けても、みんなで回せるようにしていくのがいいかなと感じています。
-

S.T
制度とか周りの環境は整っているので、自分の仕事やキャリアに不安に思うことはありません。子どもとの楽しい時間と仕事っていうのは両立できると思うので、弊社に入社していただければと思います。